なぜアメリカは「資産が育ちやすい国」なのか
アメリカって、建国からまだ250年くらいしか経っていないのに、ずっと世界の中心でお金も人も集まっている国です。
「若い国なのに、どうしてそんなに経済的な力があるの?」という疑問に答えようとすると、実は“初期設定”のところに行き着きます。つまり、建国のときから「個人の自由」と「財産を守る」という2つを徹底してきた、という話です。ここが日本を含む多くの国とちょっと違うところなんですよね。
今日は、この“初期設定”がどうやってできたのかをたどりながら、いま私たちが「米国不動産」という言葉を耳にする理由も、歴史の延長として見てみようと思います。投資の宣伝ではなく、背景を理解する回だと思ってください。
独立のときから「財産は取らせない」という意思があった
1776年の独立は、「イギリスに税ばっかり取られて不公平だ」という不満から始まりました。
つまりスタート時点で「政府が勝手に国民のお金や財産をいじるのはダメ」という空気があったんです。だからこそ、アメリカは憲法に「私有財産の権利」をはっきり書き込みました。
この“政府より個人が先”という考え方は、その後の経済制度にもずっと影響します。投資をするときに一番怖いのは「ルールが急に変わること」ですが、アメリカは歴史的にそこをかなり守ってきた国なんですね。長い時間で見ると、これは資産が集まりやすい条件になります。
西へ西へと広がった「土地が人を呼ぶ」時代
19世紀、有名な“西部開拓”が進みます。
アメリカ政府は「西の土地を使ってくれるなら、あなたのものにしていいですよ」と、人に土地を明け渡すような政策を取りました(ホームステッド法なんかがその象徴です)。この仕組みって実はすごくて、
- 土地を持つ
- 家を建てる
- 周りにお店や会社ができる
- 町ができる
- 不動産に価値がつく
という流れが自然発生するんです。つまり「所有できるようにしておく」と、人も産業も勝手に集まってきやすくなる。アメリカはこの“土地をどんどん民間に渡す”というやり方で国を大きくしていきました。
ここで“不動産を持つのは普通のことだよね”という価値観がアメリカ社会に定着していきます。これが後の郊外住宅地のブームや、今も続く持ち家志向につながっていきます。
多様な移民が「都市のエンジン」になった
もうひとつ、アメリカを語るときに外せないのが「移民の国」というポイントです。
アメリカは、世界中から人がやってくることを前提に成長してきたので、都市が縮小していくのではなく、基本的には「拡大していく」方向で歴史が進みました。ニューヨークやロサンゼルス、シカゴなどの大都市は、まさに移民の流入があったから成長した街です。
人口が増えると、必ず住宅や商業スペースが必要になります。これはすごくシンプルで、人口増加 → 住む場所の需要増 → 不動産市場の厚みが増す、という形です。
日本の地方のように「人が減るからマンションが余る」という逆方向の圧力が少ないのが、アメリカの特徴のひとつです。
20世紀は「郊外の一軒家」がアメリカの夢になった
第二次世界大戦後のアメリカでは、高速道路の整備や自動車の普及に合わせて、郊外に広い家を建てるムーブメントが起きました。
いわゆる「マイホームを持って芝生を植える」という、あのアメリカのイメージです。これは文化的な話に見えますが、不動産市場から見るとかなり重要で、
- 国民の多くが「家を持つのが当たり前」と思う
- 住宅ローン制度がそれを支える
- 建設業・不動産業が巨大産業になる
といういい循環が生まれました。家を買う人が多い国は、それだけ不動産にお金が回る仕組みが整っているということです。
危機もあったけど、ルールと規模で戻ってきた
もちろん、アメリカの不動産がいつも良かったわけではありません。
1929年の世界恐慌、2008年のリーマンショックのように、不動産や金融が原因で大きく崩れたこともあります。
それでも市場が戻ってきたのは、
- 法律が比較的透明で、権利関係を整理しやすい
- 経済規模が大きく、需要が完全には消えない
- 海外からのマネーも流れ込む
という3つの要素があったからです。つまり「一度落ちても、戻せる設計になっている国」と言えます。これは投資先として見ると、けっこう重要な視点です。
だから今でも世界のお金が向かいやすい
ここまでの歴史をざっと並べてみると、アメリカって
- 最初から財産権を守る前提で国をつくった
- 土地を民間に持たせて経済を回した
- 人口が入ってくる設計だった
- 住宅を持つ文化ができた
- ルールが比較的わかりやすい
という、資産がたまりやすい条件をわりと全部持っているんですね。
だから、世界的に見ても「不動産にお金を入れるならアメリカも候補だよね」という話になりやすい。これは別に今だけの流行ではなくて、200年くらい積み上がってきた結果だ、と言えます。
歴史を知っておくと「営業トーク」に振り回されない
日本から見ると、どうしても「アメリカ不動産=なんか儲かるらしい」みたいな表面だけの情報が先に出てきがちです。
でも本来は今日書いたように、アメリカという国の仕組み・人口動態・文化の流れがあって、その上に今のマーケットが乗っています。ここを知っておくと、たとえば
- どのエリアが伸びやすいのか
- どういう物件が好まれるのか
- なぜ権利関係をちゃんと見たほうがいいのか
といった判断がしやすくなります。歴史を知ることは、結局“焦らず選べるようになる”ことなんですよね。
個別の条件は最新で見る、がベスト
ここまでの話はあくまで「アメリカという国の土台」の話です。
実際に購入を検討するとなると、州ごとの税制や人気の都市、賃貸需要、為替のタイミングなど、もう少し細かい条件を足してあげる必要があります。ここはどうしても“今の情報”が必要になる部分なので、そこだけは別途確認してもらうのが一番安全です。
まとめ
- アメリカは建国時から財産権を守る設計だった
- 土地を民間に渡して成長してきた
- 移民が都市を押し上げてきた
- 住宅を持つ文化が需要を安定させている
- だから今も不動産にお金が入りやすい

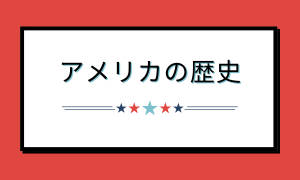

コメント